はじめての中綴じ冊子作成も安心!データ作成の基本からノンブルの付け方までご紹介
2025.09.12印刷・デザイン
本記事を読めば、中綴じ冊子の印刷データを作成方法が分かります!作成方法から細かい注意点までまとめて紹介するので、一緒に中綴じ冊子の完璧な印刷データを作成しましょう。
目次
中綴じ製本とは
A3の用紙を二つ折りにして、真ん中を針金(ホッチキス)で綴じる製本です。
針金が通る少ないページ数の冊子に適しており、見開きが綺麗に開けるため、商品カタログやパンフレット等に使用されることが多い製本方法です。この方法で製本された冊子を「中綴じ冊子」と呼びます。
中綴じ冊子のデータの作り方
①綴じ方向を決める
冊子の綴じ方向は、本文の書き方(読み進める方向)を基準として決めます。
本文が横書きの場合には「左綴じ」、本文が縦書きの場合には「右綴じ」になります。またカレンダーや資料などは、読み進めるときにページを上に向けて開く「上綴じ(天綴じ)」も使用されます。

上綴じ(天綴じ)を選択する場合には、裏表紙の向きも決定し、印刷会社に指示をしましょう。
裏表紙のデザイン配置には以下2通りのパターンがあるので、以下の図を参考に決めておきましょう。

②総ページ数を4の倍数になるように調整する
中綴じ製本は1枚の用紙に表裏に4P分印刷をしたものを2つ折りにして重ね、針金(ホチキス)で綴じています。その為、表紙裏表紙を含めた総ページ数が4の倍数以外だと製本ができません。
もしも原稿を作成する際にページ数が不足している場合には白紙ページを追加したり、目次や扉ページを作成し挿入することでページ数を調整が可能です。
③印刷可能範囲と塗り足しについて
切れてはいけない文字やデザインは仕上がりの位置よりも3㎜以上内側にレイアウトをしてください。
また、紙面の端の部分まで色や写真が入る場合には、断裁時に生じる断裁ずれを避けるために、仕上がり部分の外側3㎜部分(塗り足し)まで余分に色や写真をデザインしましょう。
🔍あわせて読みたい!
≫塗り足しとは?トンボや文字切れについても徹底解説
④ご希望に合わせてノンブルを作成する
ノンブルとは本やパンフレットなどに記載されているページ番号の事です。
主にページを表す「数字」や「P.(数字)」などと表記されます。
ノンブルは必ず記載しなければならないものではありませんが、読み手にとっては今どこを読んでいるのかというガイドのような役割を担っているので、作成している紙面にノンブルが必要か改めて検討するとよいでしょう。

ノンブルの入れ方
■ 開始ページを決定する
ノンブルは厳密にどのページから開始しなければならないという決まりはありませんが、本文の1P目をページ番号「1」にする事が一般的です。
表紙や裏表紙はページにはカウントをしませんので、ノンブルの表示=ページ数にならなくても問題はありません。

■挿入箇所について
ノンブルは基本的に右ページには右下、左ページには左下に付けます。
仮に反対に付けてしまうと本になった際にノド部分に配置され、折角のノンブルが見えにくくなってしまうために注意が必要です。

ノンブルは本文と区別がつくように、距離を開けて配置する必要があります。
しかしページの端に寄りすぎてしまうと、製本の断裁工程でノンブルが切れてしまう可能性があるので、
ノンブルの位置はページ端から4-5㎜以上は離して挿入することがおすすめです。
■ノンブルの大きさ
文字の大きさも本文と見分けがつくように、本文よりも小さな文字に設定しましょう。
デザイン等の意図がない限りノンブルはあくまで脇役なので、本文の妨げにならないようにデザインをしましょう。
💡ワンポイントアドバイス
本文内に白紙ページを入れる場合には、ページ数としては数えるもののノンブルを付けない事が一般的です。
またノンブルを左右に挿入する事が難しいようであれば、本文中央下部に挿入する方法もあります。

⑤入稿用データの作り方について
中綴じは印刷会社により入稿可能なデータ形式が異なります。
そのため入稿を考えている印刷会社のテンプレートや注意事項等をよく確認してから、推奨しているデータ形式でデータの作成を行いましょう。
以下ではよくある入稿方法を紹介いたします。
1.単ページでの入稿
綴じ方に関係なく表紙から裏表紙までページの順番通りに作成をしてください。
白紙を入れる場合には必ず白紙ページも含めて作成をするようにしましょう。
作成が終わったら表紙から裏表紙までの全ページを一括のデータで保存するか、
個々のページごとにデータを保存してください。
※印刷先が保存の方法を指定している場合には指定通りに保存をしましょう。

2.見開き面付と対面面付での入稿
「面付」とは製本するために1つのデータに2ページ分の原稿を配置する事です。
このデータの作りの場合にはページ順や表紙の配置に注意が必要です。
データ名は1つのデータに2ページ分配置するので、タイトル+ページ番号で作成すると分かりやすいです。

■見開き面付の場合
実際に冊子を開いた時の順番通りに2つの連続したページを1つのデータとしてレイアウトする方法です。
例えば、表紙・裏表紙と作成した後に本文の1ページ、2ページと順番にデータを作成します。

| 特徴 | データ作成側は、ページ順番をそのまま並べるだけなのでシンプルで面付を間違いにくい |
| 注意点 | 印刷会社側は、印刷用の対面面付に変換する作業が必要になる |
■対面面付の場合
こちらは実際に印刷をした際に隣り合うページをペアにしてレイアウトする方法です。
例えば、8P冊子の場合には表紙・裏表紙と作成した後は2ページと7ページ、3ページと6ページとペアリングをしてデータを並べます。

| 特徴 | 印刷会社側はこのまま印刷して半分に折るだけで、正しい順番の冊子が完成するので、印刷データの作成としては最適 |
| 注意点 | 配置するページ番号を間違えると、製本した際にページ順がバラバラになってしまう |
💡結局どちらを選べばいいの?
ほとんどの印刷会社では「単ページ」でも「見開き面付」のデータでも入稿可能なので、データ作成に慣れていない方はいずれかの方法で作成をすることをおすすめします。
ただし一部の印刷会社では「対面面付」での入稿を推奨している場合もあるため、入稿を検討している印刷会社がどの作成方法を推奨しているのか、事前にテンプレートやHPを見て確認をすると安心です。
中綴じ冊子のデータ作成の注意点
中心に近いページの小口レイアウトについて
ページが多い場合は表紙ページから中ページに進むにつれ、仕上げの際に断裁される幅が大きくなります。
必要な文字やデザインなどは仕上がり位置よりも3㎜以上内側に配置するようにしてください。

見開きデザインをする場合の注意点
綴じ位置付近(ノド)に左右で繋がるデザインを施すと、仕上がりの際に若干ずれてしまったり、本を閉じた際の針金により文字が読めなくなる恐れがあります。
ズレが気になる場合には、見開きのデザインは避けていただくか、綴じ位置よりも3㎜以上離してデザインをしてください。

用紙の選定について
ページ数が多い製本の場合には用紙の厚みを工夫しましょう。
用紙が薄いとすっきりとした本に仕上がり、厚みのある用紙を選定するとしっかりとした印象の本に仕上がります。
おわりに
セルマーケでは中綴じの場合には単ページ・見開き面付で入稿可能です。
それぞれデータ作成用テンプレートも展開していますので、是非活用ください!
さらにセルマーケでは注文時に中綴じ選択をすると中綴じにおすすめの用紙が簡単に選択ができます!簡単操作でDM印刷・作業・発送が手配完了しますので、ぜひお試しください。
🔍これから印刷データを入稿する方は、ぜひこちらの記事も併せてご覧ください。
≫印刷データの入稿前に確認するポイント9選
≫塗り足しとは?トンボや文字切れについても徹底解説
≫【図解でわかる】「アウトライン化」とは?手順や注意点についても分かりやすく解説
≫【illustrator(イラレ)】「リンク切れ」の原因と「リンク」「埋め込み」での対処法!
小山咲
最新記事 by 小山咲 (全て見る)
- クーポン集客を成功させる販促戦略|失敗しないコツと配布方法 - 2026年1月29日
- 【初心者必見】イラレで文字のふちどりや3D加工などの7つのテクニック紹介 - 2026年1月29日
- シニアマーケティングはWeb×DMが鍵!特徴と刺さるアプローチ手法 - 2025年12月24日

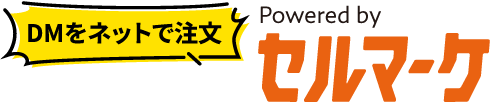
 バリアブル印刷とは?DMでの活用事例や効果を紹介!
バリアブル印刷とは?DMでの活用事例や効果を紹介! 失敗しないための印刷会社の選び方
失敗しないための印刷会社の選び方 抑えておきたい校正用語と記号
抑えておきたい校正用語と記号 要注意!法律で禁止されている広告表現・表示用語
要注意!法律で禁止されている広告表現・表示用語 印刷物で読まれるためのフォントの使い方と注意点
印刷物で読まれるためのフォントの使い方と注意点 【図解でわかる】「アウトライン化」とは?手順や注意点についても分かりやすく解説
【図解でわかる】「アウトライン化」とは?手順や注意点についても分かりやすく解説

