フォローコール営業のメリットは?DMと組み合わせて成約率アップ!
2025.07.18ダイレクトメール
紙媒体のダイレクトメール(以下:DM)は、ターゲットへ確実に情報を届けられる販促手段として、多くの企業に活用されています。しかし、DMを送付するだけでは、興味関心を持った見込み顧客を商談へと導くには不十分な場合があります。
そこで注目されているのが「フォローコール」です。
本記事では、フォローコール営業のメリットや、DMと組み合わせて活用する方法などについて解説します。
フォローコールとは?
フォローコールとは、営業活動において見込み顧客に対して何らかのマーケティング施策を行った後にする電話でのアプローチを指します。
特に、DMを活用した施策と組み合わせることで、高い成果が期待できます。
DMは、ターゲットに向けた興味喚起や情報提供に優れた手法ですが、DMの到達や開封の有無、興味・関心の度合いは、送付だけでは顧客の状況は把握できません。DMを送ったあとにフォローコールを実施することで、反応の有無を確認し、より具体的な商談につなげることができます。
DM送付後にフォローコールを行う理由
DMは、視覚的な訴求力と保存性に優れた営業手法ですが、DMだけで確実に商談につながるとは限りません。DMを受け取った側が関心を示していても、次の行動に移すきっかけを得られず、そのまま埋もれてしまうケースも多く見られます。
そこで重要となるのが、DM送付後のフォローコールです。
電話による直接の接触は、顧客の検討状況を確認し、購入意欲や関心度合いを把握するうえで効果的です。
加えて、相手の事情に合わせた提案や質問への回答をその場で行えるため、意思決定の後押しにつながります。フォローコールは、顧客の「気になってはいるが動けていない」状態を解消し、商談化へのきっかけとなるのです。
フォローコールをDMと組み合わせるメリット
DMとフォローコールを併用することで、顧客へのアプローチ効果は大きく高まります。
こちらでは、両者を組み合わせることで得られる具体的なメリットについて解説します。
反応率・商談化率の向上
DMだけでは読み流される可能性がありますが、フォローコールを加えることで顧客の行動を促進できます。
特に、DMを見て興味を持ちながらもアクションを起こしていない層に対し、電話で背中を押すことで商談化の可能性が広がります。
また、受け手が持つ疑問や懸念点にその場で答えられるため、サービスや商品の利用・導入に対するハードルを下げる効果も期待できます。
顧客との信頼関係の構築
DMと電話という二段階のアプローチにより、顧客の記憶に残りやすくなります。
DMだけでは一方通行になりがちな情報提供も、電話を通じた対話によって双方向のコミュニケーションへと発展します。この積み重ねが、企業への信頼感や親近感につながり、長期的な関係構築に寄与します。
さらに、既存顧客へのフォローコールでは、新たなニーズの発掘によってアップセル・クロスセルのチャンスも広がります。顧客理解を深める手段としても、有効なアプローチです。
成果を上げるフォローコールのポイント

フォローコールを効果的に活用するためには、単に電話をかけるだけでなく、事前準備と工夫が重要です。
以下にて、成果につなげるための具体的なポイントを解説します。
DMが到着し、開封してもらえたかの確認をする
フォローコールの冒頭では、まずDMが届いているかどうかを確認することが基本です。
この確認は、相手の関心度や資料の受け取り状況を把握するうえで重要なステップとなります。
「先日お送りした資料はお手元に届いておりますでしょうか」と問いかけ、開封済みかどうかの反応を確認しましょう。
開封している場合は、感想や関心の有無について話を広げ、次のステップへ自然に移行できます。
一方、未開封の場合でも、「資料には○○の情報が含まれています」と内容の要点を端的に伝えることで、興味を喚起できます。
あらかじめ、開封済み・未開封のどちらにも対応できる会話の流れを想定しておくことが、スムーズな対応につながります。
ゴール設定をしてから電話をかける
フォローコールを行う前に、電話の目的を明確に定めておくことが大切です。
目的が曖昧なままでは、会話の着地点が不明確になり、顧客の心に残りづらくなってしまいます。
商品理解を深めるヒアリングや訪問・オンライン商談のアポイント獲得、資料の補足説明による温度感の確認などがあります。
事前にゴールを明確にしておくことで、会話の流れを組み立てやすくなり、顧客にとっても価値ある時間に感じてもらえます。フォローコールを単なる接触ではなく、成果につながるプロセスとするためには、ゴール設計が不可欠です。
商品やサービスのメリットを端的に伝える
フォローコールは短時間で相手に情報を伝える必要があるため、商品やサービスの魅力を簡潔かつ的確に説明する必要があります。
長々と特徴を並べるのではなく、「他社にない強み」や「顧客にとってのベネフィット」に焦点を当てた説明を心がけましょう。たとえば「コスト削減に直結する」「業務工数が○○%改善される」といった具体的な数字や成果を盛り込むと、説得力が増します。
また、顧客の課題や業種に合わせたフォローを意識することで、より相手に響くアプローチになります。
ポイントは、相手の注意が集中している短い時間内に、最も伝えたい価値を届けることです。
トークスクリプトを用意する
フォローコールでは、トークスクリプトの準備が重要です。
スクリプトは、DMの内容と連動させた流れをベースに作成しましょう。
たとえば「○○のご案内資料をお送りしましたが、ご覧いただけましたか?」という導入から、「現在、○○に関して課題はありますか?」といったヒアリングに自然につなげる構成が効果的です。スクリプトがあることで、想定外の反応にも冷静に対応でき、会話の質を一定に保つことが可能になります。
また、複数の担当者が電話をかける場合でも、スクリプトがあることで対応品質の平準化が図れます。
DM送付後に使えるトークスクリプト例
フォローコールの成功率を高めるためには、顧客との会話の流れを事前にシミュレーションしておくことが有効です。以下で、実際に活用できるBtoBおよびBtoC向けのトークスクリプトの例をご紹介します。
BtoB向け
法人顧客に対しては、論理的で簡潔な説明とヒアリングを組み合わせることが重要です。
以下は、資料送付後のフォローを想定した会話例です。
| 「お世話になっております。○○株式会社の△△と申します。先日、○○に関するご案内資料を郵送いたしましたが、お手元に届いておりますでしょうか。」
(※「はい」と返答があった場合) |
このように、資料確認→価値提案→ヒアリング→商談打診の流れを意識することで、会話の自然な展開が可能になります。
BtoC向け
個人顧客に対しては、丁寧かつ親しみやすさを心がけ、サービス内容に関心を持ってもらうことが目的です。
以下は、予約や資料請求につなげるための会話例です。
| 「こんにちは。○○サービスをご案内している△△と申します。先日、郵送にてご紹介資料をお送りいたしましたが、ご覧いただけましたでしょうか?」
(※「まだ見ていない」と返答があった場合) |
BtoCでは、あくまでサービス紹介の延長線としての会話とすることで、押し売り感を排除し、信頼関係の構築につながります。
フォローコールの注意点

フォローコールは営業効果を高める有効な手段ですが、誤ったアプローチは顧客の信頼を損ねる原因となります。以下で、実施時に特に注意すべきポイントを整理します。
押し売りと受け取られないように意識する
フォローコールの目的は、DMを受け取った顧客に対し、内容の補足や理解を促すことにあります。
そのため、電話での対応は「営業」ではなく「サポート」や「情報提供」であるという立ち位置を明確にしましょう。強引な売り込みや一方的な説明は、相手に不快感を与え、信頼関係の構築を妨げます。あくまで顧客の課題や関心を引き出し、必要に応じて情報を提供するというスタンスを意識することが重要です。
また、会話の中では相手の返答や反応に合わせた柔軟な対応が求められます。トークスクリプトはあくまで補助とし、機械的な対応は避けるようにしましょう。
適切なタイミングでフォローコールを実施する
フォローコールの効果を最大化するためには、タイミングの選定が重要です。
たとえば、DMを発送してすぐに電話をかけても、まだ届いていない可能性があります。逆に、時間が空きすぎると内容が忘れられ、関連性が薄れてしまいます。
一般的には、DM到着後2~5営業日以内にコールを行うと、開封率や記憶の鮮度を維持しやすいでしょう。
また、相手の業種・業態に応じた曜日や時間帯の選定も重要です。BtoBでは平日午前中、BtoCでは夕方以降など、相手が応答しやすい時間帯を見極めてアプローチすることが効果的です。
さらに、対象者の属性に応じてコールの優先順位を設定し、効率的なリスト管理を行うことで成果につながりやすくなります。
おわりに
こちらの記事では、フォローコール営業のメリットや、DMと組み合わせて方などについて解説しました。
フォローコールは、DMと連動させることで営業活動における成約率を高める有効な手段です。
とくに、商談化の一歩手前で行うアプローチとして、顧客との関係構築や信頼獲得に大きく寄与します。
成功のためには事前のゴール設定やトークスクリプトの準備、適切なタイミングでの実施などが必要です。
一方的な営業ではなく、顧客の興味や関心に寄り添い、情報提供型の対話を心がけることが信頼構築への近道となるでしょう。
DMの印刷から発送までをWeb上で完結できるセルマーケでは、ポストカードやA4大判はがきなど、様々なサービスを提供しております。DM発送をご検討中の方はオンライン相談フォームからもお気軽にご相談ください。
小山咲
最新記事 by 小山咲 (全て見る)
- シニアマーケティングはWeb×DMが鍵!特徴と刺さるアプローチ手法 - 2025年12月24日
- 人材紹介業界の集客は郵送DMで差をつける!メリットと書き方 - 2025年12月23日
- 新規顧客獲得の戦略とプロセス|デジタル×アナログで成果を最大化 - 2025年12月23日

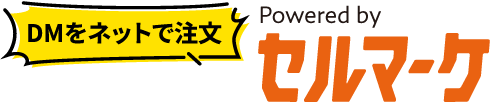
 【BtoB編】ダイレクトメールが効果的な業界・業種とは?
【BtoB編】ダイレクトメールが効果的な業界・業種とは? ハガキ(官製、往復、圧着など)の種類とビジネスでの効果的な使い方
ハガキ(官製、往復、圧着など)の種類とビジネスでの効果的な使い方 今更聞けない!DM発送で準備するもの・発送の手順とは?
今更聞けない!DM発送で準備するもの・発送の手順とは? 【郵送DMは違法?】信書とは?個人情報?DMに関する法律まとめ!
【郵送DMは違法?】信書とは?個人情報?DMに関する法律まとめ! DM営業で成果を出すには?手書きDMで他社と差別化しよう!
DM営業で成果を出すには?手書きDMで他社と差別化しよう! 【目的別】休眠顧客に響くDM例文集!反応率を高めるテクニック
【目的別】休眠顧客に響くDM例文集!反応率を高めるテクニック

