クロスメディア戦略とは?実行ポイントやメリット、DMでの活用事例をご紹介
2025.09.03 2022.10.25マーケティング
商品やサービスの販促活動をするとき、媒体選びを「なんとなく」行っていないでしょうか。とりあえずはダイレクトメール(DM)、みんなやっているからインターネット、などといった販促活動では、顧客の取りこぼしが発生してしまいます。
本記事では、DM、インターネット、TVなど複数の媒体を組み合わせて、より効果的な販促活動を実現する「クロスメディア戦略」についてご紹介します。
クロスメディア戦略とは?
クロスメディア戦略とは、1つの商品やサービスをDMやインターネット、TVなど、さまざまなメディア(媒体)を利用して販促活動することをいいます。
マルチメディア戦略と何が違うの?という疑問が湧いてくるかもしれませんが、マルチメディア戦略は、1つの商品やサービスを複数のメディアを使って販促活動すること。基本的に、メディアによってアプローチを変えるということはしません。
クロスメディア戦略でよく見かける例として、TVCMで新商品発売の告知をし、詳しい情報やキャンペーンなどについてはインターネットで検索、というものが挙げられます。単に多くのメディアを利用するというのではなく、TVならTV、インターネットならインターネットならではのメリットとデメリットを理解し、その媒体の特長を十分に活かした販促にする必要があります。つまり商品やサービスの告知から資料請求、購買に至るまでの各段階で、ふさわしいメディアを選択し組み合わせることによって、より精度の高い販促が可能になるのです。クロスメディア戦略とは、1人の消費者が購買にいたるまでの動線づくりをすることといえるでしょう。
マルチメディア戦略との違い
マルチメディア戦略と何が違うの?という疑問が湧いてくるかもしれませんが、マルチメディア戦略は、1つの商品やサービスを複数のメディアを使って販促活動することです。
基本的に、メディアによってアプローチを変えるということはしません。
クロスメディア戦略のメリット
クロスメディア戦略における3つのメリットについてご説明します。
顧客のフェーズ(潜在層、顕在層など)に合わせたアプローチが可能

一口に「顧客」といっても、それぞれ持っている欲求は違います。キッチン洗剤を例に挙げると、「キッチンをピカピカにする洗剤がほしい」と思っている人と「キッチンをピカピカにする◯◯洗剤がほしい」と思っている人がいる場合、前者を潜在層、後者を顕在層と呼びます。
潜在層とは、その商品は知らなくてもその商品のジャンルのものを購入しようとしている人、顕在層とはすでにその商品を知っていて購入まで考えている人のことです。
この両者ともに◯◯洗剤を購入してもらうためには、当然アプローチを違ったものにする必要があります。クロスメディア戦略は複数のメディアを使って顧客のフェーズに合わせた展開ができるので、単一メディアでの販促では見えてこなかった顧客を発見できたり、高いニーズを持っているのに今まで購入に結びつかなかった顧客を購入へと誘導できたりするなどのメリットがあります。
さまざまなメディアから顧客へのアプローチが可能
TVCMはとても多くの人にアプローチできますが、秒数が限られているため、詳しい情報を届けることはできません。DMは商品情報をじっくりと読んでもらえますが、住所などの個人情報がわかる人にしか送付できません。メディアにはそれぞれ一長一短ありますが、クロスメディア戦略であれば、チラシにQRコードを印刷してWEBサイトに誘導したり、TVCMで新商品告知をして雑誌に誘導したりするなど、メディアの弱点を補完し特性を活かした販促活動ができるというメリットがあります。
各メディアの得意なこと
| メディアの種類 | 得意なこと |
| TVCM | ・広範囲にリーチできる ・短時間で大きなインパクトを与える ・認知度向上に有効 |
| DM | ・詳細な商品情報を伝えられる ・ターゲット層へのピンポイントなアプローチが可能 |
| WEB広告 | ・詳細な商品説明や特典を提供できる ・ターゲットの行動履歴に基づくパーソナライズ広告 ・反響測定 |
| 雑誌 | ・特定の興味・関心を持った読者層にアプローチできる ・長期間手元に残りやすい |
| SNS | ・インタラクティブなコミュニケーションが可能 ・キャンペーンやイベントの拡散力が高い |
| ポスティング | ・地域密着型でターゲット層に効果的 ・費用対効果が高い |
このように、各メディアには得意分野があります。
クロスメディア戦略ではそれぞれの特性を活かして、顧客に最適なアプローチを行うことが可能です。
メディアごとの効果測定がしやすい
DM、TVCM、インターネットなどを組み合わせるクロスメディア戦略では、メディアごとに段階的なプロモーションを行うことができます。メディアは分かれていますが、バラバラではなくひとつの目的に向かって一連の流れがつくられているため、それぞれのメディアでの効果測定が行いやすいというメリットもあります。
時代の変化に対応しやすい
クロスメディア戦略は、新しいメディアが登場しても柔軟に対応できるため、常に最新のトレンドに合わせたアプローチが可能です。
たとえば、SNSやインフルエンサーマーケティングが広まれば、即座にこれらのメディアを取り入れ、ターゲット層に最適なメッセージを届けることができます。
これにより、時代の変化に迅速に対応でき、競争力を維持することができます。
DMとのクロスメディア戦略とは?
DMはTVCMなどに比べると多くの情報を盛り込みやすいといえますが、紙面には限りがあり、また文字数が多すぎると読む気を失わせてしまいます。もっと多くの情報を伝えたい、プレゼントキャンペーンなどに参加してほしいなどと思うときに活用したいのがインターネットです。DMの紙面に商品やキャンペーン情報などの専用ページのURLを記載することで反響率を上げることができます。
日本ダイレクトメール協会の調査によると、DMを受け取った後の行動として、商品を購入した人は2.0%、問い合わせた人は3.5%なのに対し、インターネットで調べた人は10.0%(※1)ということです。DMからインターネットへの誘導は一定の成果がでているといえます。
※1:引用元 一般社団法人日本ダイレクトメール協会「DMメディア実態調査2023」
(2025年3月31日をもって、一般社団法人日本ダイレクトメール協会は解散しました。)
特に高額商品を購入に結びつけたいときには、インターネットとの連動が有効です。一般的に高額商品を衝動買いする人は少なく、商品について詳しく調べたり、その企業やお店の理念、実際に購入した人の感想を読んだりして、自分自身が十分に納得してから購入を決意する場合が多いと思われます。インターネットであればページ数を気にせずにすみ、複雑になりがちな説明は動画で行うなどの工夫ができるので、商品のよさや企業理念などをしっかりと伝えることができます。
クロスメディア戦略の実行ポイント
クロスメディア戦略を成功させるためには、いくつかの重要なステップがあります。
以下に、戦略を効果的に組み立てるためのポイントを紹介します。
ターゲット(ペルソナ)を明確化する
まずは、ターゲットとなる顧客(ペルソナ)を明確に設定します。
ターゲットが誰で、どんなニーズを持っているのかを理解することが、戦略の基盤を作る上で重要です。
これにはアンケート調査を行い、顧客の行動パターンや悩みを把握することが有効です。
また、カスタマージャーニーマップを作成することで、顧客がどのメディアを通じて商品に接触し、どのように購入に至るかを可視化できます。
このプロセスによって、どのメディアを活用するかが明確になります。
最終目標(KGI)から逆算してメディアを選定する
次に重要なのは、戦略の最終目標(KGI)を設定することです。
売上や新規顧客獲得など、具体的な目標を決め、それを達成するために最適なメディアを選定します。
たとえば、認知度向上を目指す場合はSNSや広告を活用し、購入に結びつけるにはDMやEメールマーケティングを使うなど、目的に応じてメディアを選びます。
PDCAを回す
クロスメディア戦略では、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回すことが重要です。戦略を実行した後、結果を分析して改善点を見つけ、次の施策に活かすことで、より効果的な戦略を展開できます。
とくにメディアごとの効果を測定し、最適なアプローチを模索し続けることが大切です。
サービスや商品の改良を重ねる
クロスメディア戦略を成功させるためには、良いサービスや商品を提供することが前提です。
顧客からのフィードバックを取り入れ、サービスや商品の改良を重ねていくことで、顧客の満足度を高め、リピーターや新規顧客の獲得につなげることができます。
質の高い商品・サービスが、メディア戦略をさらに効果的にしてくれます。
以上のポイントを抑え、戦略を継続的に改善しながら進めることで、クロスメディア戦略を成功に導くことができます。
クロスメディア戦略の事例

クロスメディア戦略を成功させるためにはDMやインターネット、TVCMなど、今まで別々に展開していたものをスタートからゴールまでつなげていかなければなりません。
それには綿密な戦略が必要ですし、コストもかかります。業態やターゲット、商材などに合わせた効果的なメディアの組み合わせを考えましょう。ここでは、その事例をいくつかご紹介します。
DM・チラシ ⇒ WEBサイト ⇒ 資料・カタログ請求・来店促進
DM・チラシを使って企業やお店のWEBサイトに集客し、資料請求や来店につなげます。DMにQRコードやURLを記載し、サイト訪問によるオファー(特典)を用意するなどしてアクセスしたくなる仕組みをつくりましょう。クロスメディア戦略を意識して、DM・チラシに盛り込む内容は「インターネット集客」「来店促進」に絞り込んだものにするのがポイントです。
DM・チラシ ⇒ ECサイト
DM・チラシを使ってECサイトに集客します。今まで店舗販売だけだった商品をECサイトでも販売する場合、まずはECサイトの存在を顧客に知らせないことにははじまりません。DM・チラシであれば、広く確実に告知することができます。
WEBサイト + SEO対策 ⇒ 資料・カタログ請求
SEO対策によって企業やお店のWEBサイトに集客し、そこから資料請求につなげます。取り扱い商品がとても多い場合や商品の色をきちんと見せたい場合は、インターネットよりも紙の資料の方が見やすいし、魅力も伝わりやすくなります。資料請求のハードルを下げるために、個人情報の入力項目が多くなりすぎないようにするなど、工夫してみるといいかもしれません。
おわりに
本記事では、DM、インターネット、TVなど複数の媒体を組み合わせて、より効果的な販促活動を実現する「クロスメディア戦略」についてご紹介しました。
クロスメディア戦略を取り入れる際に考えたいことは、下記の3点です。
- 何のメディアで集客するか
- 何のメディアに集客するか
- 顧客にどのような行動をとってもらいたいのか
これらを戦略立てて考えていくことで、活用するメディアや、メディアをいくつ組み合わせるのかが決まってきます。
そのためには、それぞれのメディアの特性をよく理解しておくことが必要です。DMの場合、顧客情報を把握しておかなければ送ることができないため、まずは顧客に情報を登録させる仕組みを用意しておく必要があるでしょう。そして、直接手元に届けることができる特性を意識して他のメディアとのクロスメディア戦略に取り組んでみてください。
教えて!DM先生 編集部
最新記事 by 教えて!DM先生 編集部 (全て見る)
- 【2026年(令和八年・午年)版】ビジネス年賀状の書き方・マナー・例文を紹介! - 2023年9月1日
- メディアミックスとは?基本的な戦略とクロスメディアとの違い - 2023年8月24日
- 【例文・デザイン例あり!】通信販売(EC)業界での効果的なDM作成方法 - 2023年8月3日

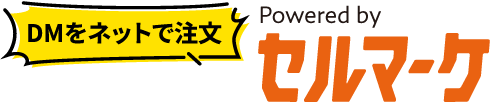
 ダイレクトマーケティングの特徴と手法8選!メリットと注意点も解説
ダイレクトマーケティングの特徴と手法8選!メリットと注意点も解説 ダイレクトメールの効果を測定する方法とは?
ダイレクトメールの効果を測定する方法とは? BtoB向けのDMを成功させるコツ|BtoC向けとの違いや活用シーンを解説
BtoB向けのDMを成功させるコツ|BtoC向けとの違いや活用シーンを解説 要注意!法律で禁止されている広告表現・表示用語
要注意!法律で禁止されている広告表現・表示用語 顧客分析(RFM分析・デシル分析)を活用したマーケティング手法とは?
顧客分析(RFM分析・デシル分析)を活用したマーケティング手法とは? テストマーケティングとは?メリットとその方法
テストマーケティングとは?メリットとその方法

