DMの反応率の平均は?測定方法や反応率を上げる方法を解説!
2025.09.29 2023.08.22事例・効果測定
マーケティング活動において欠かすことのできないダイレクトメール(以下:DM)。
活用している企業も多いですが、「実際に送って効果があるの?」「そもそも効果はどうやって測るの?」と思われている方も多いかと思います。
こちらの記事では、効果測定の計算方法や、反応率UPに繋がるポイントをご紹介していきます!
目次
反応率とは
反応率とは、送付したDMのうち、商品を購入するなど何らかの反応があったDMの割合のことを言います。
開封率と混同されることが多いですが、開封率は開封・閲読したDMの割合のことであるため、その後の反応を指す反応率とは異なります。
反応率は行動喚起率、レスポンス率とも言われます。
🔍あわせて読みたい!
≫DM(ダイレクトメール)の開封率は?開封率を上げる方法10選
反応率の種類は?
元々反応率は、DMを送付した顧客のなかで「商品を購入した」「資料を請求した」「問い合わせをした」など直接的な行動をとった顧客の割合のことを指していましたが
最新の調査では最新の調査では「インターネットで調べた」「話題にした」「来店した」といった間接的な行動をとった割合も増加しているとの結果が出ています。
すぐに商品の購入などの結果に繋がらずとも、WEBへの誘導や、口コミによる宣伝効果も期待できると言えるでしょう。
反応率の目安は?
DMを発送する先のターゲットによっても数値は変わってきますが、一般的な反応率の目安は下記のように言われています。
・新規顧客への発送:0.5~1%
・見込み顧客への発送:1~10%
・既存顧客への発送:5~15%
あくまでも目安の数値となりますので、工夫をすることで結果は変わります。
効果測定を行うには

作者:Nuthawut/stock.adobe.com
DMは送って終了ではあまり意味がありません。
発送することでどのくらい効果が得られるのか都度検証することで、今後更に効果を高めるための改善点も見えてきます。では、効果を測るためにはどうしたらよいのでしょうか?
①総DM費を確認
まずは制作費から発送費まで、1回のDM発送にかかるコストを確認しましょう。
DM発送には意外と多くのコストがかかっていますので、全て確認し計算しましょう。
依頼する業者によっても料金が異なる為、業者選定は重要なポイントとなります。
ネット上でDMの印刷・作業・発送の注文が完結できるセルマーケでは、低コスト且つ印刷から発送まで一回の注文で完結できるのでオススメです!
②損益分岐点(BEP)を確認
損益分岐点とは、コストを利益でカバーし損益0の状態になることを指す言葉で、BEP(Break Even Pointの略)とも呼ばれています。
ここでは、①で算出した総DM費を回収するために、最低何件受注する必要があるのかを計算しましょう。
例えば、総DM費が350万円で粗利単価が5,000円の場合
【350万円 ÷ 5,000円 = 700件】という計算になり、最低でも700件受注できれば利益がマイナスになることはないということがわかります。
実際の受注数がBEPの数値よりも高ければ黒字となり、費用対効果が高いと言えるでしょう。
③受注件数で損益を算出
受注件数を基準に損益を算出することで、DM施策の収益性を正確に把握できます。
例えば、発送数に対する反応数を確認した後、実際に受注へつながった件数を算出します。
そのうえで、平均単価と掛け合わせて売上を求め、総DM費と比較することで利益を明確にできます。
分析を繰り返すことで、単なる反応率の数値評価にとどまらず、収益改善に直結するデータを得られます。
受注件数ベースの算出は、施策の持続可能性を判断する上でも有効です。
④反応率を確認
実際に発送したDMの反応率は、下記計算式にあてはめると確認することができます。
例えば、100,000通のDMを発送し5,000件の申し込みがあった場合
【5,000件 ÷ 100,000通 × 100 = 5%】という計算になり、反応率が5%だということが算出できます。
⑤CPR(Cost Per Response)の分析
CPR(Cost Per Response)は、顧客からの反応を1件獲得するためにかかった費用を指します。
DMを発送した際、商品購入や資料請求、問い合わせなどが反応になります。
例えば、10万円の費用をかけて5件の反応があった場合、CPRは10万円÷5件=2万円/件になります。
CPRを高めるためには、広告宣伝費を抑えるか反応数を向上させる必要があります。
とはいえ、広告宣伝費を削るとDMを発送するユーザー数に影響を及ぼしてしまうため、反応数向上を目指すと良いでしょう。
CPRは費用対効果の一環として考えられる指標のため、目標CPRを設定している企業は多いです。
CPR・BEP・反応率の関係性
DM施策の収益性を評価する際、CPR・BEP・反応率は密接に関連します。
反応率が高いほど1件あたりの獲得コストは下がり、必要な損益分岐点のハードルも低くなります。
逆に反応率が低下すると、反応1件あたりのコストが上昇し、損益分岐に必要な売上・件数も増加。
つまり、反応率は施策全体の効率や利益に直結し、CPRやBEPはその影響を数値で示します。
これらの数値を継続的に把握することで、DM施策の費用対効果や改善余地を正確に判断できます。
実際には何倍もの効果がある・・・?
前述した通り、「商品を購入した」「資料を請求した」など直接的な行動をとった割合だけではなく、
「インターネットで調べた」「話題にした」といった間接的な行動をとった割合も増加しており、どうしても効果測定ができないものもあります。
そのため、実際には計測した反応率の何倍もの効果があると言われているのです。
反応率を計測するには?
セルマーケには、DMのアクセス履歴が計測できる「DMLPメーカー」というサービスがあります。DMLPメーカーを利用すれば、これまでわからなかった見込客の行動を把握できるようになるのです!
LP制作だけでも相場で数10万円の制作費用が掛かりますが、DMLPメーカーでは①②③を全てセットで5万円(税別)~でご注文いただくことが可能です。詳細はサービスページよりご確認ください。
≫DMLPメーカーのサービスページはこちら>>
DMの費用対効果を高めるための考え方
DMの施策においては、単純に反応率を追うだけでなく、費用対効果の向上を意識することが重要です。
効果を最大化しながらコストを抑えることで、より持続可能なマーケティング活動が実現できます。
以下にて、DMの費用対効果を高めるための考え方をまとめました。
反応率を高める
反応率を高めるには、まずターゲットの精度を上げることが欠かせません。
顧客データを分析し、購買履歴や属性に応じてセグメントを設定すると、内容がより響きやすくなります。
また、受け取る相手に合わせたパーソナライズを施すことで、関心を引きやすくなります。
さらに、限定割引や先着特典など具体的なオファーを設けると、行動につながる確率を高められます。
訴求内容を継続的に検証し、効果が出やすい切り口を磨く姿勢も大切です。
コストを下げる
発送数や紙質を最適化するほか、はがき型にするなど郵送形態を工夫することで、発送費を削減できます。
また、リストを精査して反応が見込めない層を外せば、無駄な費用を防ぎつつ反応率も改善できます。
印刷~発送まで一貫して依頼可能なサービスを利用し、業務効率化とコスト圧縮を同時に実現できます。
このように、反応率向上とコスト削減を両輪で進めることが、費用対効果を高める鍵となります。
【法人/個人宛】反応率を上げる方法は?

作者:oatawa.adobe.com
今回は、反応率UPに繋がる6つのポイントをご紹介します!
①ターゲットを絞り込む
DMの反応率を上げるには、まず対象となる顧客を明確にすることが不可欠です。
年齢や性別、居住地といった基本属性に加え、購買履歴や利用頻度といったデータを分析することで、関心の高い層を抽出できます。
このようにセグメントを細かく分けると、訴求内容をより適切に設計でき、不要な発送を避けることも可能です。
結果として、配布数は少なくても効率的に成果を高めることができます。
②お得感のあるオファーをつける【個人宛】
受け取り手にとってお得感のあるオファーを付ける ことも効果的です。
マーケティングでのオファーとは、一般的に割引や特典のことをいい、 ターゲットユーザーに実行してもらいたいアクションの後押しができるようなオファーをつけると、反応率UPに繋がります。
特に個人宛DMでは、受け取った人が「今すぐ行動したい」と思えるような限定性や希少性を盛り込むと効果が高まります。
例えば「先着100名限定」や「今月末まで有効」といった訴求は、検討を後回しにしがちな顧客に対しても購買意欲を喚起できます。また、誕生日や記念日など特定のタイミングに合わせて特典を設けると、パーソナルな関係性を演出できます。
こうしたオファーは単なる割引以上に、顧客が特別扱いされていると感じる要素となり、長期的なファン化にも寄与します。お得感と同時に「あなた向けの特典」というメッセージを加えることが、個人宛DMにおいては大きな差別化要因になります。
🔍あわせて読みたい!
≫反響率アップに必須! ダイレクトメールのオファーの種類と特徴
③発送する時期を見直す【個人宛】
DMを発送する時期によっても反応率に影響が出てきます。
では、具体的に何月を狙うのがよいのでしょうか?
・1月、4月、9月 =新たな取り組みや新生活をスタートさせる時期
・6月、12月 =ボーナス月
・5月、6月、10月、12月、1月 =母の日、父の日、ハロウィン、クリスマス、正月
上記のような時期は、一般的に消費意欲が高まる傾向にあると言われており、
新生活が始まる1月4月9月は通販関係のDMが、季節のイベント時期ではセールやキャンペーンのDMの反応率が高いとされています。
実際にDMを発送するタイミングとしては、直前ではお金の使い道が既に決まっている可能性もあるため、
1ヶ月程度前に届くよう計画するとよいでしょう。
ただし、ゴールデンウイークやお盆などの大型連休中やその直後は、不在率も高く出費が重なる時期ということもあり、反応率が低い傾向にあるため避けた方が無難です。
🔍あわせて読みたい!
≫DMの発送タイミングを変えるだけで開封率・反響率は上がる?
④発送するタイミングを見直す
発送する時期を決めたら、その月の中でも発送するタイミングを見直してみましょう。
法人宛て・個人宛てでタイミングが異なるため、下記を参考にしてみてください。
■法人宛(toB)
一般的に、1週間のうち月曜日が新しい取り組みへのモチベーションが最も高まる曜日と言われています。
月曜日に読んでもらえるよう、土曜日・日曜日には到着するよう発送するとよいでしょう。
ただし、月末・月初は多くの企業が忙しい時期となるため、避けた方が無難です。
さらにBtoBのDMでは、単なる商品紹介だけでなく、業界動向や導入事例を盛り込むことで信頼性を高められます。例えば「同業他社の成功事例」や「無料セミナーへの招待」を併せて記載すると、読み手にとって実務的なメリットを感じやすくなります。
営業担当者の顔写真や直通連絡先を添えるのも効果的で、具体的なアクションにつながりやすくなります。
■個人宛(toC)
toCでは平日より時間に余裕のある土・日曜日に届くよう発送すると、反応率が高くなると言われています。
火・水曜日あたりには発送できるよう準備するとよいでしょう。
加えて個人宛DMでは、試供品や限定キャンペーンを活用すると高い効果を得られます。
例えば「サンプル同封」や「初回購入限定割引」のように、実際に商品を試すきっかけを提供することで購買意欲を喚起できます。
また、QRコードを掲載して特設ページへ誘導すると、オンライン施策との連動も可能になります。
「期間限定」等といった要素を盛り込むことで、受け取り手に具体的な行動を促しやすくなります。
⑤複数のメディアと組み合わせる【法人/個人宛共通】
DMとWEB、テレビ、メルマガなど1つのみならず、複数のメディアを組み合わせた販促活動のことをクロスメディア戦略と言います。
例えば、DMから自社のWEBサイトへ誘導することで、DMだけでは伝えきれなかった情報を届けることができ、また、様々なメディアを組み合わせることで、DMとの親和性の低い顧客へのアプローチにも繋がります。
ただし、とにかく多くのメディアを利用すれば良いというわけではなく、ターゲットや目的に合わせふさわしい組み合わせにする必要があり、
各媒体の特徴を十分に活かすことで、多くのターゲットからレスポンスを得ることができるでしょう。
日本DM協会の調査でも、DMを受け取ったあとの行動として、商品の購入や利用をした人が3.4%だったのに対し、ネットで調べた人は8.0%だったとの結果も出ており、WEBへの誘導は反応率を高めることに繋がると言えます。
🔍あわせて読みたい!
≫クロスメディア戦略とは?実行ポイントやメリット、DMでの活用事例をご紹介
⑥デザインの工夫
DMの効果を高めるには、内容だけでなくデザイン面での工夫も重要です。
まず視認性を意識し、情報の優先度に応じて文字サイズや色を変えることで、伝えたい要素を直感的に理解してもらえます。
また、表紙や冒頭にアイキャッチとなるビジュアルを配置すると、受け取り手の関心を引きやすくなります。
レイアウトはシンプルで余白を活かし、読み手がストレスなく情報を追える設計が理想です。
さらに、写真や図解を活用することで、サービスの特徴やメリットをイメージとして伝えられます。
これらの工夫を組み合わせることで、反応率向上につながる効果的なDMを制作できます。
セルマーケでは高い反響率の獲得をサポート
DMの印刷~発送が注文可能なWEBサービス「セルマーケ」では、DMに関するさまざまなサービスを提供しています。
DMの送り先にお困りの場合、1件あたり5円で法人のDMのリストを販売しています。
ユーザーの行動を把握したい、DMからの流入を計測したい場合、「DMLPメーカー」のご用意もございます。
使用するLPやQRコードの作成、アクセスレポートの提出なども承っています。
気持ちが伝わりやすい【ウルトラ手書きレター】
毎日、多くのDMがお客様のもとに送られています。さまざまなデザインが施されているDMですが、手に取って興味を持ってもらわなければ、中身を見られないまま捨てられる可能性があります。
読者の目を引く手法のひとつとして、“手書き”が挙げられます。
しかし、1枚ずつ手書きでDMを作成すると、多くの時間と費用がかかってしまうものです。
そこで、想いが伝わりやすい手書きDMサービスである「ウルトラ手書きレター」もお勧めです。
通常のDMよりも開封率が高い傾向にある為、アフターフォローや新規顧客開拓など、さまざまな用途・目的でご利用いただけます。
ミニマム50通から送付できるため、スモールスタートやお試し施策としても最適です。
おわりに
本記事では、DMの反応率について解説しました。
発送都度しっかりと効果測定を行い改良を重ねていくことで、DMの効果も高まっていくはずです。
企画の段階でも、反応率UPのポイントを押さえ制作してみてください。
反応率は上げたいけど、やっぱり一番はコストが気になる・・・という方にはセルマーケがオススメです!
「DMをもっと手軽に、もっと身近に。」をモットーに、短納期・低価格のダイレクトメール印刷発送をご提供しております!ぜひご活用ください。
三輪姫乃
最新記事 by 三輪姫乃 (全て見る)
- DMの宛名ラベル・宛名印字の種類は?印象がUPする書き方も紹介 - 2025年11月28日
- DMで介護施設の利用者・スタッフを増やす方法とは? - 2025年11月26日
- 【人気キャラクターとの商品コラボ】効果や費用、販売までの手順を解説! - 2025年10月20日

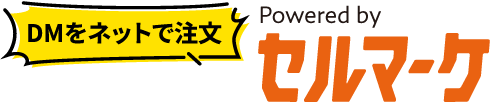
 ダイレクトメール(DM)の効果測定指標と計算方法について
ダイレクトメール(DM)の効果測定指標と計算方法について ダイレクトメールの効果を測定する方法とは?
ダイレクトメールの効果を測定する方法とは? サンプリングの効果は?手法やメリット・デメリットを徹底解説!
サンプリングの効果は?手法やメリット・デメリットを徹底解説! 【例文・デザイン例あり!】学習塾・予備校業界での効果的なDM作成方法
【例文・デザイン例あり!】学習塾・予備校業界での効果的なDM作成方法 秋【9月,10月,11月】おすすめの時候の挨拶・結びの言葉
秋【9月,10月,11月】おすすめの時候の挨拶・結びの言葉 冬【12月,1月,2月】おすすめの時候の挨拶・結びの言葉
冬【12月,1月,2月】おすすめの時候の挨拶・結びの言葉

