ゆうパックとレターパックの違いは?料金やサービスを解説!
2025.07.10 2025.01.22郵便サービス
「ゆうパック」と「レターパック」どちらも郵便局のサービスですが、違いはご存知でしょうか?
本記事ではサービスの違いや、料金やサイズなどの基本情報を紹介します!
目次
ゆうパックとレターパックの違い
ゆうパックとレターパック、どのような違いがあるのか比較してみましょう。
基本情報
| ゆうパック | レターパックプラス | レターパックライト | |
| サイズ | 3辺(縦・横・高さの外寸)合計170cm以内 | 340×248㎜ (A4ファイルサイズ) |
340×248㎜ (A4ファイルサイズ) 厚さ3㎝以内 |
| 重量 | 25㎏以内 | 4㎏以内 | |
| 料金 | サイズ・配達距離により異なる | 全国一律600円(税込) | 全国一律430円(税込) |
| 追跡 | あり | ||
| 受領印 | あり | なし | |
| お届け | 対面手渡し | 郵便受けに投函 | |
| 未配達 | 不在時 | 郵便受けに入らない場合 | |
| 再配達 | 不在表を確認のうえ、配達郵便局へ依頼 | ||
| 補償 | あり(30万円まで) | なし | |
料金は?
・ゆうパック:サイズ・配達距離により異なる
・レターパック:全国一律
「レターパックライト」は430円、「レターパックプラス」は600円と全国一律の料金となっているのに対し、ゆうパックは荷物のサイズや配達先への距離により異なります。
封筒で送れる?
・ゆうパック:封筒でもOK
・レターパック:封筒NG
レターパックは専用のケースを購入する必要があるのに対し、ゆうパックは特に決まりがありません。規定サイズ内であればダンボールはもちろん、封筒や宅配袋に入れて送ることも可能です。
配達日時の指定はできる?
・ゆうパック:指定可能
・レターパック:指定不可
どちらも土日祝日も配達を行うサービスですが、レターパックは配達日やお届け時間の指定はできません。通販やオークションでの商品発送にレターパックを利用する場合には、日時指定ができないことを念頭に入れておきましょう。
信書は発送できる?
・ゆうパック:発送不可
・レターパック:発送可能
レターパックでは信書を送ることができますが、ゆうパックではNGとなっています。信書を送れるのは、レターパックや郵便など一部サービスに限られていますので注意しましょう。
損害補償はある?
・ゆうパック:補償あり
・レターパック:補償なし
荷物が郵便局の責任で汚れたり壊れてしまった場合、ゆうパックは30万円までの補償がついています。レターパックは補償はついていないため、貴重品を送る場合はゆうパックを利用すると良いでしょう。
ここからは、それぞれのサービス内容を詳しく紹介していきます。
おすすめの利用シーン
ゆうパック
・配達日時を指定したい
ゆうパックは、配達日・配達時間帯を指定することが可能です。土日祝日も配達を行っているので、急ぎの発送にも適しています。
・小さいサイズで重量のある荷物を発送したい
各サイズごとの重量制限がないため、小さいサイズで重さのある荷物を発送する際にオススメです。
レターパック
・信書などの書類を対面受取で送りたい
レターパックは信書を発送できるだけでなく、レターパックプラスの場合は対面(手渡し)で届けられるサービスです。ポスト投函では不安という場合に活用すると良いでしょう。
・厚みがある荷物を送りたい
レターパックプラスでは、4㎏以内であれば厚さの制限がないため、厚みのあるものを送る時にオススメです。

ゆうパックのサービス詳細
ゆうパックは、郵便局の宅配サービスです。土日祝日・配達日時の指定が可能で、3辺(縦・横・高さの外寸)の合計が170cm以下・重さ25㎏までの荷物を発送することができます。梱包資材には指定がないので、ダンボールだけでなく封筒や宅配袋を使用しても問題ありません。
| ゆうパック | |
| サイズ | 3辺(縦・横・高さの外寸)合計170cm以内 |
| 重量 | 25㎏以内 |
| 料金 | サイズ・配達距離により異なる |
| 追跡 | あり |
| 受領印 | あり |
| お届け | 対面手渡し |
| 未配達 | 不在時 |
| 再配達 | 不在表を確認のうえ、配達郵便局へ依頼 |
| 補償 | あり(30万円まで) |
100個以上発送したい場合はDM-Sゆうパックがオススメ!
発送代行歴20年以上の発送代行大手ディーエムソリューションズ(株)には、日本郵便と特別契約しているDM-Sゆうパックがあります。
「1度に100個以上発送したい」「EC通販で日々出荷が必要」など、梱包作業~発送までを丸投げすると安価にゆうパックの発送が可能となり、とてもお得に発送することができます。
ゆうパックの発送を検討されている方、こちらのお問合せフォームよりご相談ください!
利用するメリット
■各サイズごとの重量制限がない
サイズにより最大重量が変わらないため、小さいサイズで重さのある荷物を発送するのに適しています。
■割引サービスがある
ゆうパックには下記3種の割引サービスがあり、お得に発送することが可能です。
・持込割引(割引額:120円/個)
郵便局・コンビニなどのゆうパック取扱所に荷物を持込することで適用
・同一あて先割引(割引額:60円/個)
1年以内に発送したゆうパックまたは重量ゆうパックの「ご依頼主控え」を添えて、同じあて先・種類の荷物を差し出す際に適用
・複数口割引(割引額:60円/個)
同じあて先・種類のものを2個以上差し出しする場合に適用
■コンビニからも差出し可能
ゆうパックはローソン、ローソンストア100、ミニストップ、セイコーマートからでも発送ができるため、近くに該当のコンビニがある場合は嬉しいサービスです。また、郵便局へ集荷を依頼することも可能なので、重い荷物を発送する場合などに便利です。
利用方法
①送り状(宅配伝票)を準備する
まずは送り状を用意しましょう。発行方法は3パターンあります。
・自宅のパソコンで印刷
・スマートフォンアプリで入力し郵便局で発行
・郵便局で複写式の伝票をもらい手書きする
②発送準備
ダンボール等へ荷物を梱包し、送り状(宅配伝票)を貼付します。ゆうパックの梱包用品は郵便局にも用意がありますが、特に指定はないので、自身で手配したダンボールや封筒などを使用してもOKです。準備が完了したら、郵便局やコンビニへ持ち込むか、郵便局へ集荷を依頼し差し出しましょう。
③宛先へ到着
配達日時に指定がない場合、1~2日程度かけ宛先へ到着します。

レターパックのサービス詳細
レターパックは、A4サイズ・4kgまで全国一律料金で発送可能なサービスです。信書の同封も可能で、土日・祝日も含め毎日配達されます。
レターパックには、対面で届けて受領印をもらう「レターパックプラス」と、郵便受けに届ける「レターパックライト」の2種あり、厚さの規定や料金が異なります
| レターパックプラス | レターパックライト | |
| サイズ | 340×248㎜ (A4ファイルサイズ) |
340×248㎜ (A4ファイルサイズ) 厚さ3㎝以内 |
| 重量 | 4㎏以内 | |
| 料金 | 全国一律600円(税込) | 全国一律430円(税込) |
| 追跡 | あり | |
| 受領印 | あり | なし |
| お届け | 対面手渡し | 郵便受けに投函 |
| 未配達 | 不在時 | 郵便受けに入らない場合 |
| 再配達 | 不在表を確認のうえ、配達郵便局へ依頼 | |
| 補償 | なし | なし |
利用するメリット
■信書も発送可能
信書を送ることができるサービスは限られていますが、レターパックはOKです!
■郵便ポストへ投函可能
レターパックの場合、郵便局での差し出しも可能ですが、郵便ポストへの投函でも発送可能です。「近くに郵便局がない」「日中郵便局へ行く暇がない」という方にも嬉しいサービスとなっています。
■事前に専用ケースを購入しストックできる
「レターパックプラス」「レターパックライト」どちらも専用ケースへ荷物を入れ発送する必要があります。専用ケースを事前に購入しストックしておけば、送るたびに購入する必要はなく、効率良く発送することができます。
利用方法
①レターパックの専用ケースを購入
「レターパックプラス」「レターパックライト」どちらも専用ケースの購入が必要です。郵便局の窓口やコンビニエンスストアなどの郵便切手類販売所、郵便局のネットショップで購入可能です。
②発送準備
購入した専用ケースへ宛先情報などを記入し、荷物を封入します。切手の貼付は不要です。
準備が完了したら、郵便ポストへ投函もしくは郵便局へ差し出しを行います。
③宛先へ到着
1~3日程度かけ宛先へ到着します。レターパックライトはポストへお届け、レターパックプラスは対面でのお渡しとなります。
おわりに
今回紹介した「ゆうパック」「レターパック」に関して、下記記事でも詳しく解説していますのでご覧ください!
🔍あわせて読みたい!
≫ゆうパックとは?サイズや料金などの特徴を徹底解説!
≫レターパックとは?プラス・ライトの違いや料金、送り方を解説
郵便局以外にも様々な発送方法があるので、「どのサービスを選んだら良いのかわからない」という方は、ディーエムソリューションズ(株)へご相談ください!
最適な発送方法をご案内いたします。お問合せはこちらのフォームから≫
三輪姫乃
最新記事 by 三輪姫乃 (全て見る)
- DMの宛名ラベル・宛名印字の種類は?印象がUPする書き方も紹介 - 2025年11月28日
- DMで介護施設の利用者・スタッフを増やす方法とは? - 2025年11月26日
- 【人気キャラクターとの商品コラボ】効果や費用、販売までの手順を解説! - 2025年10月20日

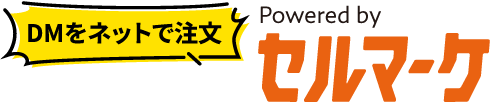
 郵便・ゆうパック・ゆうメールで割引?日本郵便の各種割引制度について
郵便・ゆうパック・ゆうメールで割引?日本郵便の各種割引制度について クリックポストとは?料金や発送方法、ゆうメールとの違いを解説
クリックポストとは?料金や発送方法、ゆうメールとの違いを解説 年賀状DMを送付するメリット4選!顧客のアクションにつなげるコツ
年賀状DMを送付するメリット4選!顧客のアクションにつなげるコツ ゆうゆう窓口でできること|DM発送は依頼できる?
ゆうゆう窓口でできること|DM発送は依頼できる? 【2026年4月~】大口特約ゆうメールがまた値上がり‼来年度に向けてのDM発送準備
【2026年4月~】大口特約ゆうメールがまた値上がり‼来年度に向けてのDM発送準備 ゆうパックとゆうパケット違いは?料金やサービスを解説!
ゆうパックとゆうパケット違いは?料金やサービスを解説!

