料金後納郵便?料金別納郵便?特徴や利用条件を詳しく解説!
2024.10.03 2023.07.24郵便サービス
DMの発送方法を考えたときに、「郵便」を思い浮かべる方も多いと思います。
DMは普通の郵便と違って、発送部数が多くなるのが特徴です。そこで、少しでもコストを抑えるために押さえておきたいのが「料金後納」「料金別納」という方法です。
ただ、この2つにはどんな違いがあって、どのように使い分ければいいかはご存じですか?
ここでは、料金後納と料金別納の違いや、表示する上での注意点について解説します。基本的な考え方を理解して、最適な発送方法を選んでくださいね。
※掲載情報は2024年2月19日時点での情報です。最新情報は、日本郵便公式サイトをご確認ください。
目次
料金後納郵便とは?

作成者:Andrey Popov/stock.adobe.com
「料金後納」とは、郵便料金の支払い方法の1つで、「翌月に郵便料金を支払う仕組み」です。1ヶ月分の郵便費用を翌月に一括払いをすることができるので、都度郵便料金を精算したり、切手を貼ったりする手間を省くことができます。差し出し条件を満たすことで月間割引制度の対象となり、発送コストを抑えることもできます。
料金後納郵便を利用するには料金後納郵便マークが必要ですが、送り方によってマークの表示方法も様々な決まりがあります。料金後納郵便マークの表示方法については、記事の最後の方で詳しく説明します。
利用条件
料金後納郵便を利用するためには3つの条件があります。
①郵便物や荷物を毎月50個以上差し出す
②取扱郵便局にて承認を受ける
③1カ月間に差し出す郵便物や荷物の、概算額の2倍以上の額を担保として提供する(現金・有価証券・金融機関の保証など)
差し出し個数の条件に関しては、ゆうメール・ゆうパケット以外の荷物や国際小包であれば月10個以上、EMS(国際スピード郵便)であれば月4個以上の差し出しで利用することが可能です。
申請から利用までの流れ
①郵便局の承認を受ける
まずは事前に郵便局から承認を受けます。書類手続きが必要となるので、取扱郵便局の指示に従い申請を行いましょう。
窓口では「後納郵便物等差出表」などの必要書類を受け取り、記入のうえ申請します。
書類は郵便局のHPからもダウンロードできるので、事前に記入しておくと申請時間を短縮できます!
申請が完了すると、「ゆうびんビズカード」が届きます。郵便物を差し出す際必要となるので、大切に保管しておきましょう。
②郵便物を差し出す
郵便局へ差し出しを行う際は、
・郵便物に「料金後納郵便」の表記が記載されているか
・「後納郵便物等差出表」の記入が済んでいるか
を確認し、郵便物に後納郵便物等差出表・ゆうびんビズカードを添えて差し出します。
24時間いつでもお近くのポスト(郵便差出箱)へ投函できる「後納ポストイン」というサービスもあります。
郵便局へ行って差し出しする時間がない…!という方は、ぜひ利用してみてください。
③支払い
1か月分の郵便料金を、まとめて翌月末日までに指定口座へ振り込みます。
事前に郵便局から承認を受ければ、口座振替も可能ですので、経理の手間も省けます!
口座振替の場合は、翌月20日が引き落とし日となるのでご注意ください。
料金後納郵便のメリット・デメリット
料金後納郵便を利用することのメリット・デメリットを紹介いたします!
メリット
・切手貼付の手間を軽減
郵便を封書で差し出す際、通常であれば料金に応じて1通1通切手を貼付する必要がありますが、大量に送る場合は手間になってしまいます。
料金後納郵便を利用すれば、予め表記を印刷した封筒を使用したり、宛名と一緒に印字するなど、作業効率化に繋がります。
また、切手をストックしておく必要もないため、在庫管理の手間も軽減できます。
・経理業務の省力化
郵便物を差し出す都度支払いを行う必要がなく、1カ月分まとめて支払いができるため、経理業務を省力化することが可能です。
デメリット
・事前に郵便局の承認が必要
利用したいと思ってすぐに利用できるものではなく、事前に郵便局へ書類を提出し申請を行い、承認を得る必要があります。
承認が下りるまでにある程度時間を要するため、申請した日に利用できるというわけでもありません。
・毎月50通以上の差し出しが必要
郵便物や荷物を月50通も送らない場合や、大量に送る時もあるが毎月ではない場合は利用することができません。
通数の条件があるため、誰でも利用できるというわけではありません。
・差し出せる郵便局が決まっている
全国どの郵便局でも差し出しができるわけではなく、集荷業務を行っている郵便局に限られます。
希望の郵便局が対応しているのか、事前に電話等で確認しておくと良いでしょう。
料金別納郵便とは?

作成者:molenira/stock.adobe.com
「料金別納」とは、「発送の都度に郵便費用を一括で支払う仕組み」のことです。料金後納と同じく切手を貼る手間はありませんが、料金はその都度現金か郵便切手で支払う必要があります。
料金別納を申し込む条件
料金後納郵便を利用するためには2つの条件があります。
①差し出す郵便物や荷物はすべて同じ料金
②同時に10個以上差し出す
条件が少なく、事前の承認を受ける必要もないため、料金後納郵便よりも気軽に利用可能です。
また、ゆうパックや国際小包、EMSの場合は1通でも料金別納が利用できます。
郵便はがきを大量に差し出す場合、印刷・作業・発送業務などお手間になりますよね。
セルマーケならネットから注文するだけ!印刷~発送まで、面倒な作業をすべてお任せできます。
詳しくはコチラ。
料金別納を利用する流れ
料金後納と違って、料金別納はその都度窓口に申し入れるだけでいいので、事前に申請を行う必要はありません。
・郵便物に「料金別納郵便」の表記が記載されているか
・「別納郵便物等差出票」の記入が済んでいるか
を確認し、郵便物と一緒に窓口に持っていけばOKです。ポストへの投函はできないので注意しましょう。
料金別納郵便のメリット・デメリット
料金別納郵便を利用することのメリット・デメリットを紹介いたします!
メリット
・切手貼付の手間を軽減
料金後納郵便同様、封筒に料金別納郵便のマークを表記していれば切手を貼付する必要はありません。
少量でも貼付作業は手間になるので、作業効率化に繋がります!
・差し出し状況が記録できる
料金別納郵便を利用し郵便物を差し出す際、「別納郵便物等差出表」へ発送日や差し出し通数、合計金額などを記入する必要があります。
記入した情報は記録として残るため、経理処理をスムーズに行うことが可能です。
デメリット
・差し出せる郵便局が決まっている
料金後納郵便同様、全国どの郵便局でも差し出しができるわけではありません。
近くの郵便局で取り扱いがあるのか、事前に電話等で問い合わせておくと良いでしょう。
・同じ料金の差し出しが必要
差し出す郵便物は、全て同じ料金である必要があります。
ただし、料金ごとに分けて差し出す場合は、全て同じ料金でなくても大丈夫です。
30通のうち、10通が140円、20通が180円というように、同じ料金でまとめた時10通以上になっていればOKです。
それぞれの違いとは?
料金後納郵便と料金別納郵便の違いがよく分かるように、表にまとめました。
| 料金後納 | 料金別納 | |
| 用途 | DMなど、毎月定期的に発送する郵便物 | セールや新商品のお知らせなど、不定期に発送する郵便物 |
| 事前申込 | 必要 | 不要 |
| 支払い | 1ヶ月分を翌日一括して入金。 銀行振込・口座振替から選べる |
発送の都度現金払いか、郵便切手での支払い |
| 利用条件 | 毎月50通以上発送すること | 同時に同一料金の郵便を10通以上発送すること |
| 割引 | 同時差出割引(1,000通以上) | 同時差出割引(1,000通以上) |
| 局印(スタンプ表示) | 自分で準備する必要がある | 郵便局にあるスタンプを利用可能 |
料金後納も料金別納も、郵便料金の計算を簡単にし、発送業務や経理業務を効率化できる方法です。
💡どちらを選べばよいのか迷ったときは
「定期的に郵便物を発送するか?」という観点で考えてみてください。毎月DMを発送する場合、荷物の発送が多い場合、請求書などを郵送している場合などは、料金後納郵便を利用することで経費削減・業務効率化が見込めます。支払いも翌月に一括払いできるので、企業の経理面でもメリットがあります。
💡毎月の郵便差出し件数にバラつきがある場合は
料金別納郵便の利用がおすすめです。季節ごとに出すDMや、セールや新商品の案内、カタログの送付など、同じ形の郵便物を同時にまとめて差し出す場合に切手を貼る手間を省くことができます。料金別納の表示は郵便局でスタンプを押すこともできますが、事前に郵便物に印刷してしまえばさらに効率的に発送業務を進められます。発送の都度現金で支払う必要がありますが、その都度発送日・発送通数・金額の記録を残すことができます。
それぞれの違いを理解して、どちらを選択するか決めてましょう。
ポストカードDMを送るなら、印刷から郵便差出までWEB注文で完結できるセルマーケがオススメです。
100通以上の発送で注文でき、通数やDMの内容に応じて、最適な割引が適応されます!
ポストカードDMの商品ページはコチラ。
料金後納・料金別納郵便マークの表示方法
最後に、料金後納・料金別納の表示方法についてご紹介します。基本的な表示方法は共通しています。
表示場所

料金後納・料金別納の表示は、郵便物の左上部(横長の形式であれば、右上部)に記載します。
形状・大きさ

形は円形か四角形を選ぶことができます。大きさについては、円形の場合は直径を2~3センチ、四角形の場合は各辺の長さを2~3センチに設定する必要があります。
料金後納または別納の上に書いてある「差出し事業所名」の部分には、郵便物や荷物を差し出す郵便局名を表示します。ただ、郵便物に差出人の氏名や住所を明記してある場合は、表記を省略できます。
広告表示も可能

四角形や円形の下2分の1部分に、差出人の業務を示す広告を記載することも可能です。
送達日数の表示

マークの中に引かれている線の本数は、郵便物の送達日数と割引率を示しています。
・通常の郵便と同じ配達日数の場合:1本線
・3日程度の猶予を認める場合:2本線
・7日程度の猶予を認める場合:3本線
を引く決まりになっています。
いずれも、線の間隔は1~2ミリにすることが決められています。
2本線の場合は「特割」、3本線の場合は「特特」と呼ばれ、配達まで時間が掛かる分、料金の割引率も高いという仕組みです。この割引を使えるのは、広告郵便物(同一内容で大量に作成された印刷物)と区分郵便物(事前に郵便区番号ごとに区分された郵便物)、第三種郵便物(事前に承認を受けた定期刊行物)です。
DMなどの広告郵便物の場合、事前に広告郵便申請を行うことで、より割引率を高めることができます。承認請求書に印刷物の見本を添えて承認を受ける必要があるので、余裕を持った発送スケジュールを組んだ上で活用しましょう。
🔍あわせて読みたい!
≫郵便・ゆうパック・ゆうメールで割引?日本郵便の各種割引制度について
おわりに
料金後納と料金別納を上手に活用することで、DMの発送業務を安く効率的に行うことができます。
事前申請の有無や支払いの方法、利用するための最低発送数に違いがあるので、自社の郵便発送状況を確認の上、どちらを選択するか決めましょう。
ちなみに、セルマーケは郵便局への事前申請は不要!印刷から郵便局差出までをWEB上で一括注文できるのでとってもオススメです。
教えて!DM先生 編集部
最新記事 by 教えて!DM先生 編集部 (全て見る)
- 【2025年(令和七年/巳年)版】ビジネス年賀状の書き方・マナー・例文を紹介! - 2023年9月1日
- メディアミックスとは?基本的な戦略とクロスメディアとの違い - 2023年8月24日
- 【例文・デザイン例あり!】通信販売(EC)業界での効果的なDM作成方法 - 2023年8月3日

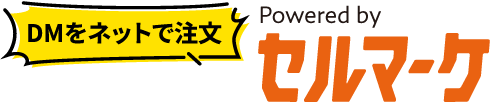
 ゆうメールとは?料金やサイズ、配達日数、普通郵便との違いを解説
ゆうメールとは?料金やサイズ、配達日数、普通郵便との違いを解説 郵便・ゆうパック・ゆうメールで割引?日本郵便の各種割引制度について
郵便・ゆうパック・ゆうメールで割引?日本郵便の各種割引制度について 郵便・ゆうメールに必要なマークの種類と注意点とは?
郵便・ゆうメールに必要なマークの種類と注意点とは? 現金書留・一般書留・簡易書留とは?それぞれの違いと使い分けについて
現金書留・一般書留・簡易書留とは?それぞれの違いと使い分けについて 第三種郵便・第四種郵便とは?規格や送料などの特徴を徹底解説!
第三種郵便・第四種郵便とは?規格や送料などの特徴を徹底解説! 区分郵便物(郵便番号区分・バルク区分)とは?割引率と区分結束について
区分郵便物(郵便番号区分・バルク区分)とは?割引率と区分結束について

